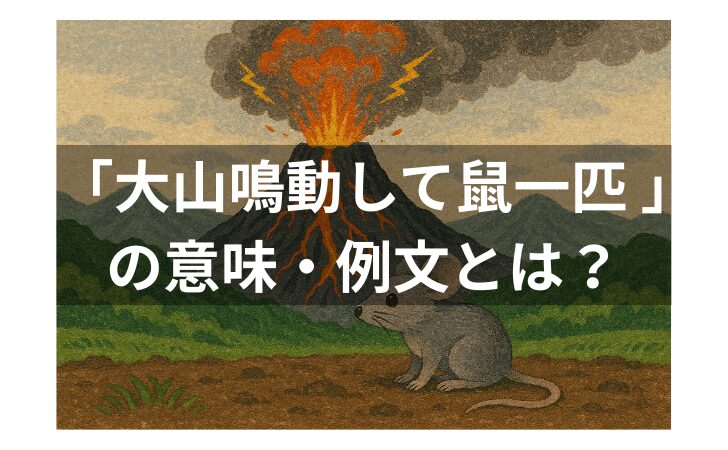「大山鳴動して鼠一匹(たいざんめいどうしてねずみいっぴき)」ということわざを聞いたことはありますか?
何か大事件が起こるかのような大騒ぎの末に、結局は取るに足らない結果に終わってしまった…そんな場面で使われることのある言葉です。
この記事では、「大山鳴動して鼠一匹」の意味や由来、具体的な使い方や言い換え表現、さらには英語・中国語での表現まで詳しく解説していきます。
ことわざ「大山鳴動して鼠一匹」の読み・意味は?
意味:前ぶれのみ大きく、結果は小さいこと。出典:デイリーコンサイス国語辞典
このことわざの読み方は「たいざんめいどうしてねずみいっぴき」です。
大きな音を立てて山がゆれたけど、出てきたのはたった一匹のネズミだけだったということから、
意味は、「大騒ぎしたわりに、結果は非常に小さく取るに足らないものであったことのたとえ」です。
期待が大きかっただけに、拍子抜けしてしまうような結果に対して使われます。
「大山」と「泰山」どちらが正しい?
このことわざは、「泰山鳴動して鼠一匹」と表記されることもあります。
「泰山(たいざん)」は中国で最も尊ばれる山のひとつで、「大山」と同じように非常に大きな存在の象徴とされています。
したがって、「大山」でも「泰山」でも意味は同じで、いずれも「大きな山が激しく揺れ動いたのに出てきたのはたった一匹の鼠だった」という期待外れの比喩として使われます。
「大山鳴動して鼠一匹」の例文・使い方
この章では「大山鳴動して鼠一匹」ということわざの例文をご紹介します。
日常生活での使い方
ビジネスシーンでの使い方
学校や勉強に関する使い方
使い方のポイントと注意点
- やや皮肉を含む表現なので、目上の人やフォーマルな場面では注意が必要です。
- 冗談っぽく使うときには、柔らかい言い回しにしたり、口調を和らげたりするとよいでしょう。
- 書き言葉として文章に入れると、文学的な雰囲気が加わることもあります。
ポイントとしては、皮肉や落胆のニュアンスを含むため、フォーマルな場面では使い方に注意が必要です。
「大山鳴動して鼠一匹」の同義語・言い換えや類義語は?
この章では「大山鳴動して鼠一匹」の同義語・言い換えや類義語似た意味をもつことわざや表現をご紹介します。
| 同義語・類義語 | 意味 | 例文 |
| 空騒ぎ(からさわぎ) | 騒いだわりに実際には大したことが起きないこと。「大山鳴動して鼠一匹」と同様に、結果が伴わない大げさな騒ぎを表します。ビジネスやニュースの現場でもよく使われます。 | 大規模なリコールかと思ったが、実際は一部の部品交換だけの空騒ぎだった。 |
| 拍子抜け(ひょうしぬけ) | 期待していたほどのことが起きず、気が抜けること。期待外れの結果に対して使います。 | 緊張して面接に臨んだのに、雑談だけで終わって拍子抜けした。 |
| 肩透かし(かたすかし) | 期待していたことが外れ、がっかりさせられること。「拍子抜け」と近い意味ですが、「肩透かし」は意図的にかわされたような印象を与える場合もあります。相手の期待を裏切る点で「大山鳴動して鼠一匹」との共通点があります。 | 新製品の発表会だったのに、何の目新しさもなくて肩透かしだった。 |
| 張り子の虎(はりこのとら) | 見かけ倒しで実際には弱いこと。こちらは「大山鳴動して鼠一匹」と比べて、“見た目だけが立派”というニュアンスが強めです。結果の小ささというより、実態のなさに注目した表現です。 | 強面の上司かと思いきや、部下に何も言えない張り子の虎だった。 |
| 期待はずれ(きたいはずれ) | 期待していた通りの結果にならず、がっかりすること。「期待はずれ」は日常会話でもよく使われる言い回しで、シンプルに「期待と違った」という意味を表します。 | 話題の映画だったが、内容は期待はずれだった。 |
「大山鳴動して鼠一匹」の由来・語源は?
この章では、「大山鳴動して鼠一匹」の由来・語源について解説します。
ラテン語の詩が語源!?
「大山鳴動して鼠一匹」は、実は古代ローマの詩人ホラティウス(Horatius)の詩の一節が語源とされています。
ホラティウスの詩集『詩論(Ars Poetica)』の中に、以下のような表現が登場します。
”Parturient montes, nascetur ridiculus mus.”
意味:「山々が産気づいたが、生まれたのは滑稽な鼠だった。」
この詩では、「大きな山がうなりを上げて動き出し、何かとてつもないものが生まれると思いきや、出てきたのはたった一匹の鼠だった」という比喩を用いて、内容のわりに過剰な表現をすることへの風刺が込められています。
このホラティウスの表現は、明治時代以降の西洋文学紹介・翻訳活動の中で、日本語として定着したという説が最も有力です。
実際、明治・大正期の文献や評論の中にこの言い回しが見られはじめます。
「大山鳴動して鼠一匹」に関するQ&A
- 「大山鳴動して鼠一匹 」の対義語は?
- 「大山鳴動して鼠一匹 」を英語、中国語で言うと?
「大山鳴動して鼠一匹 」に関するよくある疑問は上記の通りです。
ここからそれぞれの疑問について詳しく解説していきます。
「大山鳴動して鼠一匹 」の対義語は?
「大山鳴動して鼠一匹」は、「大きな騒ぎや前ぶれのわりに、結果が非常に小さい」「期待外れだった」という意味のことわざです。
では、その逆の意味――「たいした期待もなかったのに、意外と大きな成果が出た」「予想を上回る結果になった」といった対義語には、どのようなことわざがあるのでしょうか?
次に代表的なものをご紹介します。
| 対義語 | 意味 | 例文 |
| 瓢箪から駒(ひょうたんからこま) | ありえないと思っていたことが現実に起こるたとえ。意外なものから大きな成果が現れるという点で逆の意味合いを持ちます。 |
|
「大山鳴動して鼠一匹 」を英語・中国語で言うと?
| 英語表現 | 意味 | 例文 |
| Much ado about nothing | adoとは騒ぎ、骨折り、面倒という意味で、直訳としては「何もないことに大騒ぎ」、大きな騒ぎをしているが、実際は大したことではない。 | Everyone was talking about the new product launch, but it turned out to be just a basic update—much ado about nothing.(新製品発表で大騒ぎだったけど、結局は基本的な更新だけで、大山鳴動して鼠一匹だった。) |
| A storm in a teacup | 直訳は「ティーカップの中の嵐」、実際には取るに足らないことを、過剰に騒ぎ立てること。 | The media made it sound like a scandal, but it was just a misunderstanding—a storm in a teacup.(マスコミは大スキャンダルみたいに報じたけど、ただの誤解で、大山鳴動して鼠一匹だった。) |
| Great cry and little wool | 直訳は「大声で鳴くが、羊毛は少し」、大きな騒ぎや宣伝のわりに、実りが少ないこと。 | They promised revolutionary changes, but nothing much happened—great cry and little wool.(革命的な改革だと大騒ぎしてたけど、結局何も変わらなかった。大山鳴動して鼠一匹だったよ。) |
| 中国語表現 | 意味 | 例文 |
| 雷声大,雨点小(léi shēng dà, yǔ diǎn xiǎo) | 雷の音は大きいのに、雨はほんの少し=大げさな前触れに対して、実際の結果が小さいこと。 | 他们说这次发布会很厉害,结果雷声大,雨点小。 (彼らは今回の発表会がすごいと言っていたが、大山鳴動して鼠一匹だった。) |
| 雷声大作,结果一场空(léi shēng dà zuò, jié guǒ yì chǎng kōng) | 大きな音を立てたが、結果は何もなかった=大げさなだけで実体がないこと。 | 这项改革宣传得很热闹,最后却雷声大作,结果一场空。 (この改革は盛大に宣伝されたが、結果は大山鳴動して鼠一匹だった。) |
まとめ:「大山鳴動して鼠一匹」の意味・例文を理解しよう
「大山鳴動して鼠一匹」は、大きな期待や騒ぎに対して、結果が極めて小さいことを表すことわざです。
短い言葉で、期待と現実のギャップを鋭く皮肉ることができ、日常会話からビジネスまで幅広く使えます。
そのシンプルさの中に、風刺や批評のニュアンスも含まれており、期待外れの場面を的確に表現できます。
意味や使い方を正しく理解しておけば、表現の幅が広がり、言葉の説得力も高まるでしょう。